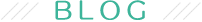リハビリテーション 5月号(NO.573)「退院により見放されたと感じる」ことの不幸
リハビリテーション 5月号(NO.573)
「退院により見放されたと感じる」ことの不幸 畑 恒土
健康の概念の変化を持ち出すまでもなく、医療の目的は目の前の人を幸せにすることであり、病気を治すことだけが目的ではない、「手術は成功しましたが命は助かりませんでした」などと発言する医師にとって、手術の目的はその人の幸せではない。 このような医師は論外であるが、患者さんの側でも病院の機能をよく理解する必要がある。
高機能病院の宿命
病院は様々な検査・治療機器をそろえ、様々な専門職が同時に働くことで病気と闘いやすい環境を作っている。しかし多くの中核病院の設備投資には多額の税金が使われており、その機能を効率的に発揮する責務を併せ持っている。そのため病人の自由が制限されるだけでなく、より機能を発揮すべき患者さんを優先せざる得ないことになる。 そこで急性期を過ぎると次の病院への転医が必要になるが、その病院がその機能だけでなくサービスも劣る場合が少なくない。高機能病院の医師はその板挟みになるわけだが、これは高機能病院を優遇した制度上の問題でありそれをその責任を病院の医師に押し付けるのは酷である。
病院の医師の問題
一方、病院で病気と闘う医師は、病気を治すことができなくなりもはや自らの腕が発揮しようがないと思った時点で、患者さんに対して無力であることが多いい。どのような病状にあったとしてもその人にとってより幸せな状態を作り出すことが求められるが、病院の中の医療しか知らない医師にそのために打つ手は思いつかない。また治療に効果が得られない場合病院には役割がないといってもよい。自分に役割がなくなった時、自分の役割はないといえない医師がたくさんいる。そういう医師は病院の医療が最善だと思っている医師であり、最善でない医療の世界に患者を送り込むことは患者を見放すことと同じである。そのような医師がどのような言葉を用いたとしても患者さんは見放されたと感じて当然である。病院の中しか知らない医師にとって、医療は病気との戦いであって、その人の幸せを考えるゆとりはないように思われる。
在宅医療の選択
在宅医療の環境はその人ひとりひとりで大きく異なり、その環境の良し悪しで人を幸せにもすれば不幸にもする。私たち在宅医療関係者の役割は、家にいたいと願う本人家族に、できる限りよい環境を作り出すことだと思っている。どんな状況であっても、もう少しいい状態を作ることは可能であり、そういう意味で私たちは決して患者さんを見放すことはない。しかしその選択は、本人の希望と家族の希望にゆだねるべきであり決して病院から追い出された結果として選ばれるべきではない。残念ながら、在宅医療でできることを病院の医師が知らない場合が多いために、積極的に在宅医療を選択できない患者さんが多いことである。私たちは病院から追い出されるように在宅医療を開始して、「結果として」よかったといっていただく患者さん家族にもしばしばお目にかかる。
癌の終末期の患者さん
ここで紹介する81歳の久保田さんはお寺の住職である。多くの檀家さんから信頼されたかたで、本堂と鐘つき堂の間の藤棚が自慢だった。3月のある日、腎がんと脳転移が発見され、治療を受けることになったが、副作用が強く表れ1か月ほどで治療は中止された。 家に帰って本堂にお参りがしたいと願う父親を連れて帰ってあげたいという次女の思いを受けて私たちが関わることになった。初めて開催された病院でのカンファレンスでは肝心の一つ年下の奥さまが何も知らないことがわかり、まず家族で情報共有をしていただくこととした。その後自宅で話し合いを設けたがその時点で病院の医師から状態が悪くなったので退院は困難との説明がされたとのことだった。(検査データは最悪であり、白血球が3万まで増え、反対に強い貧血を認め血色素は3.5グラムと正常の4分の一程度であった。)
看取りのためだけでも家に連れて帰ることは可能だと説明したところ家族の意見は連れて帰ることで一致した。そこで翌日から在宅医療が開始されることになった。病院では1日1000mlの点滴と11種類の内服薬を飲まされていた。帰宅後すぐに点滴を抜去し、内服薬も中止し、ステロイドホルモンと胃薬だけ静脈注射することとし、あとは看護師の指導に任せた。看護師は口の中のケアの仕方を家族に教え、おむつ交換や体位変換の仕方も教えたがそれ以外は自分たちがやるから気にしなくていいと説明した。
翌日、本人の希望にそって白衣(はくえ)に着替えて本堂へのお参りを済ませた。この日には五日ぶりにお粥とみそ汁を口にした。退院3日目には家族全員に清拭、更衣、足浴、陰部洗浄の指導が終わり、全員がマスターした。同級生が何人も集まり昔話に花を咲かせ、カボチャ、レバーペースト豆腐、バナナなどを食べたと報告していただいた。そんな日が続き6日目には本人がお経をあげたいから歩くと言い出し、形だけだがリハビリを開始することになった。9日目になって意識がだんだん薄れ始め、飲み込みもむつかしくなっていった。看護師は、時々息を休んだり、大きなため息をついたりするかもしれないといったことを説明して、予想外の変化により家族が不安を抱かないように気遣いながらケアを共に行った。 退院して12日目、今日の夕方から私が3日間留守にするが、ほかの同僚医師が同じように対応すると説明したが、その時間に合わせるかのように息を引き取られた。 この間私たちは癌と闘ったわけではない、むしろ何もしなかった。しかしそのことにより食べられなかった食事が食べられるようになり、友達と話をし、家族と別れの時間を過ごすことができた。実は病院で最も苦手なことは、何もしないということなのである。
介護への誤解
15年前に介護保険が導入されたとき、一つのうたい文句が介護の社会化であった。
家族が介護の責任を一身に追うのでなく社会全体で介護に責任を持とうとのことだと思われるが、実は介護の位置づけが大きく間違っていること気かがつかなくてはならない。
介護を家族の肩代わりと考えるのであれば介護は高い評価を受けられない。 家族の誰かが倒れれば、家族はその日から介護者になる。何の経験も無い人間がいきなり介護者になるのであるから全くの素人である、家族の肩代わりができないが家族の介護の肩代わりであればそれほど難しいことではない。
私たちは生まれたばかりのときはともかくとして、ある程度たってからは自分のケアは自分で行ってきた。朝起きて顔を洗い、着替え、食事の用意をして食事を済ませ、用を足して仕事に出かける。そのすべてについてその人なりの快適なやり方があり、それを人にやってもらいたいとは思わない。 けがなどで今までできたことができなくなった時に介護が必要になる。私たちが必要とする介護は自分ができなくなった時に自分がやってきたように応援してくれることであり、最善は自分でできるようにして頂くことである。なぜかといえば自分以上に自分のことを知り、自分のやり方以上に快適に介護してくれる人などいないのだから。
終わりに
在宅医療に25年携わって学んだことは、医療の不確実性と、人間一人一人が持つ生命力の偉大さである。今まで良かれと思い行われてきた多くの医療行為が実はむしろ体に負担をかけていたということが何度も繰り返されている。褥瘡への消毒、副作用で消えていった薬の数々など数えあげればきりがない。 何もしないことは難しい。風邪で受診した患者さんに薬を処方しないで返すことがしばしばあるが、そのためには非常に多くの時間を必要とする。 在宅医療でやりたくてもできないためにやらなかった結果として驚くほどいい結果が得られることは少なくない。このことはまだ病院の医師には実感としてつかめていないと思う。